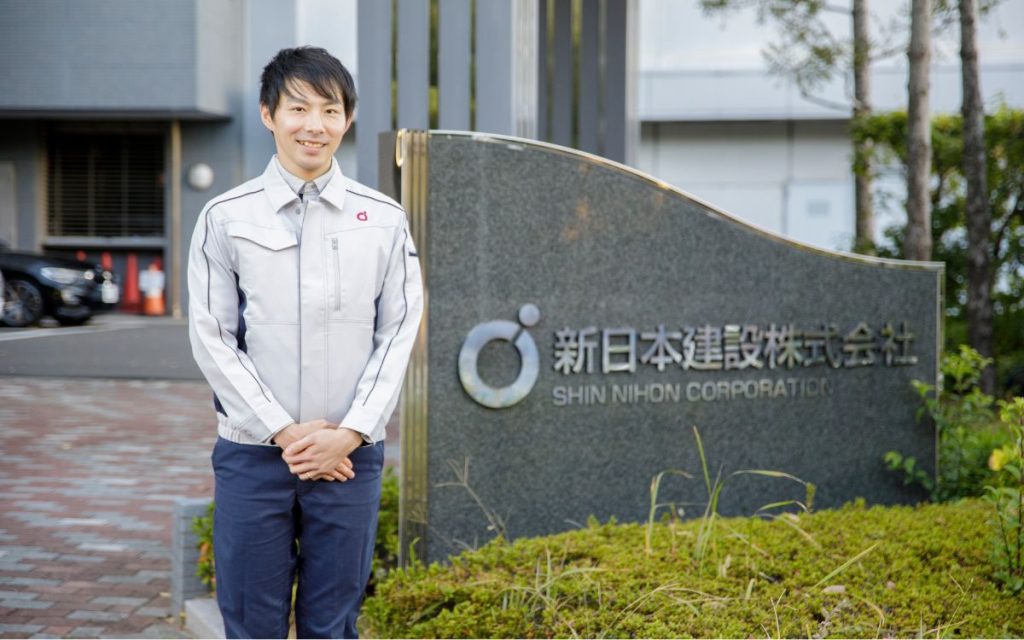
業界では異例の若さで所長に挑戦。新日本建設だから、背伸びができる。
業界では異例の若さで所長に挑戦。
新日本建設だから、背伸びができる。
このストーリーのポイント
- 面接の対応で、人を大切にする社風を感じて入社
- 所長は一国一城の主。現場のすべてに責任を負う
- 先輩の背中を追いかけながら、次は追いかけられる立場へ
40代、50代の所長が建設業界の常識。だが、新日本建設では30歳前後の所長が活躍している。背伸びできる環境だからこそ、得られる成長も大きい。
新日本建設株式会社
安達 聖太
工事統括本部
第二工事本部 工事第一部
2018年入社
理工学部建築都市環境学系卒
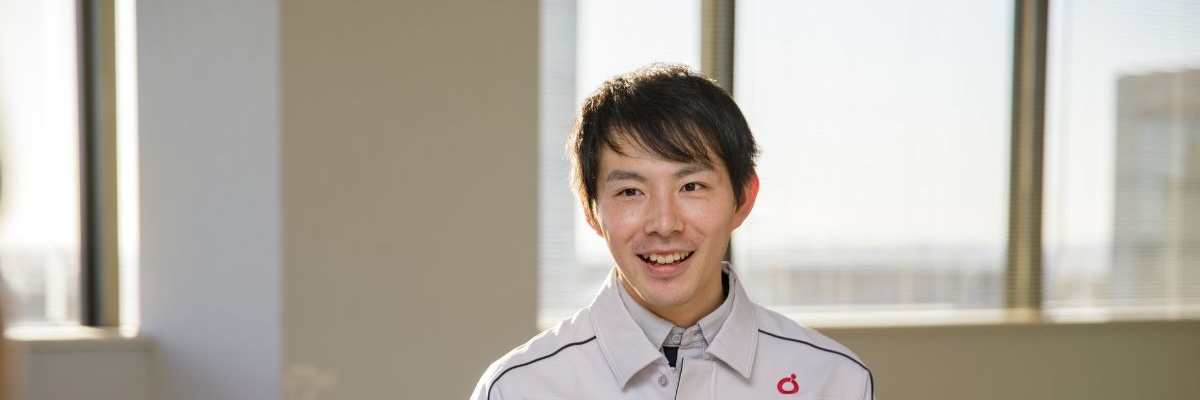
千葉県出身。採用時の対応のよさに惹かれて、入社を決める。施工管理としてこれまで多くの物件に携わり、入社6年目から所長を務める。
実家近くで親孝行がしたかった
学生時代には卓球部に所属し、2年生の後半から3年生は3つのキャンパスにまたがるチームのまとめ役として総合主将を務めました。3キャンパス合計で部員数は約100人。まとめ上げることは簡単ではなかったですが、先輩にアドバイスをいただきながら全員の気持ちを一つにすることに取り組みました。
人数が多いので技量はバラバラで、モチベーションも人それぞれ。おかげで人をまとめ上げる力はずいぶんと鍛えられたと思います。
建築系の学科で学んでいたことに加え、卓球部での総合主将での経験から、施工現場で人をまとめる施工管理の仕事に興味を持ちました。大勢の人の前で話した経験も活かせると思いました。
そこで大手建設会社のインターンシップに参加。先輩社員から職人さんとの触れ合いなどのエピソードを聞き、ぜひ自分でもやってみたいと思ったのです。当時、建設業界は3Kのイメージが強く、また、職人さんは怖いという思い込みもありましたが、そんなことは一方的な思い込みに過ぎないということも知りました。
新日本建設に決めたのは、勤務地が首都圏限定という点が大きかったです。私は千葉県に生まれ育ったのでこの地を離れがたく、実家の近くで親孝行をしたいという気持ちがありました。
決め手となったのは、選考過程での対応です。非常にスピード感があって、1回目の面接が終わって1、2時間後には次回の面接の案内があり、内定の通知も最終面接の直後にいただきました。合否の結果はどうであれ、連絡が早ければ早いほど、就活生の負担は軽くて済みます。人事部の対応に接し、就活生のことを親身に考えてくれている姿勢を通じて、人を大切にする社風を感じ、入社を決めました。

現場を自分の意図どおりに動かしていく
入社6年目から施工現場の所長を務めています。現在の物件が、私にとって所長としての最初の現場。都内・江戸川区にある比較的小規模なマンションの現場で、職人さんの数は40人から50人といったところ。所長として初めて担当する現場としてはちょうどいい規模ではないかと感じています。
所長は文字通り現場の責任者です。最も大切な業務は工事のコスト管理と施工に必要な施工図の作成、施主や設計事務所との連絡などです。新日本建設の「自社製販一貫体制」による物件でしたら社内の設計担当者との調整で済むのですが、これはデベロッパーから施工を請け負った案件であるため、設計は外部の事務所となり、そのため調整には少し手間がかかるわけです。特に施主との調整では、建設の専門家ではない方に向けてわかりやすく解説する気配りも必要です。
安全や品質、納期の管理などは部下である次席に任せ、私は全体を広く見ることを心がけています。
初めての所長ということで、赴任までは大きな不安がありました。それまでコスト管理、つまりお金の管理は経験したことがなかったので、果たして自分にできるか、自信がなかったのです。
次席として所長の下で働いていたときはコストのことはあまり気にせず、納期や安全を考えたら必要な手はすぐに打てばいいと考えていました。しかし所長となった今、当たり前なんですが、何をするにもコストがかかることに改めて驚いています。だから必要な施策があっても、別の方法で代替できないかと考えるようになりました。
例えば外壁用に指定された塗料が生産終了であると判明したとき、設計事務所は代わりの塗料を提案してきましたが、コスト面から価格の安いものを探し出して、こちらから逆提案をしたことがありました。ささいなことですが、日々のこうした積み重ねがコスト管理の基本です。
所長としての醍醐味は、何といっても建設現場を自分でコントロールし、前に進めていけることです。例えば協力業者さんも私の指示どおりに動いてくれますし、私の考えた工程どおりに作業が進んでいくのはとても気持ちいいです。もちろん現場が順調に進むには心地よい雰囲気づくりが欠かせませんから、業者さん等に決して威圧的に対応することはありません。皆さんに気持ちよく働いてもらいたいと考えています。
いい空気の現場は安全・工事・納期の管理もうまくいき、コスト面でも問題は少ないものです。

職人さんに教わり、育ててもらった
入社してからこれまで4つの現場で施工管理を務めてきました。印象に残っているのは2つ目の特別養護老人ホームの施工現場です。入社2年目から3年にかけて担当しました。
なぜ印象に残っているかというと、とても苦労した現場だったからです。ここで私は初めて次席として働くことになったのですが、まだ入社2年目ですから経験不足ははっきりしており、大きな不安を抱えながらの仕事となりました。
若くても責任あるポジションを任せ、背伸びさせることで育てていこうというのは、新日本建設ならではの育て方だと感じます。入社5、6年でも所長になれるなんて、40代半ばで所長になるのが一般的なスーパーゼネコンでは、考えられないことではないでしょうか。
この現場で特に大変だったのが、施工図面を読み込んで職人さんたちに正しく伝えることでした。
例えば図目に書かれてある型枠の寸法が少しでも不明瞭だと、職人さんは私に質問してきます。それを聞いた私は施工図のもとになった設計図に立ち返って読み込んでから、回答します。そのとき、ちょっとでも回答が遅いと工事は遅れてしまうし、私も“頼りにならない”と見なされてしまうわけです。
ただ、自分の経験不足、知識不足ははっきりしていましたから、職人さんに教えを請うことも多かったです。見栄を張らず、素直に頭を下げて、教えてくださいとお願いすると、職人さんも喜んで教えてくれました。こうした積み重ねで徐々に次席としての力が磨かれていったと思います。
これまで経験してきた3つの現場では、ずっと同じ所長のもとで働きました。自分もこの所長のようになりたいと思うようになったのも、自然なことだったと思います。
この所長の何が凄かったかというと、先を読む力です。現場の状況を把握し、図面を読んで、「この先、こんなことが起きるから準備をしておくように」という指示をしてくれるのです。1ヵ月先、2ヵ月先ではなく、竣工までの流れをすべて見通しているのでしょう。
私も数多くの現場を経験することで、この所長のような人材になりたいと思っています

より大規模な現場の所長に挑戦したい
建設現場での効率化や省力化は長年の大きなテーマです。課題解消のために、新日本建設でもデジタル化には力を入れており、AI議事録の導入やスマホへの端末の置き換えなどを進めています。ただ、作業者の高齢化はいかんともしがたく、主力として現場を支えてくれている50代以上のベテランの職人さんとなると、デジタル化への抵抗は少なくないようです。
建設業のデジタル化を進めていくことは私の役割ではありませんが、本社の施策を現場で着実に遂行することには取り組んでいきたいと思います。
現在の目標は、まず所長として初めての現場である現在の建物を確実に竣工まで進めていくことです。今はちょうど30歳なので、40歳、50歳になったらもっと大規模な現場で自信を持って牽引できる所長になっていたいと考えています。かつて私が所長の背中に憧れて成長を後押しされたように、いつか私が後輩たちから目標にされるような存在になれたら嬉しいですね。
また、建設現場でのトップは所長ですから、本社で所長を束ねる立場にも挑戦したいです。
私が一緒に働きたいと思うのは、人の言葉に素直に耳を傾けられる人材です。同期と話していても、素直に話が聞けるか、そうでないかでは成長の速度に違いが出て、2年目になる頃には大きな差が開いていることもあると、仲間たちも感じているようです。
そして何よりも大切なのが、向上心。常に前向きにいろんなことを吸収し、成長しようとする姿勢をお持ちの方と、現場で一緒に仕事ができたら嬉しく思います。




